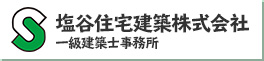第四回目のコラムです。
今回は、かなり深刻になってきている日本の人口減少&高齢化について、
そして、それに対応した国の住宅政策についてお話したいと思います。
日本の高齢化のスピードは、世界でも稀に見る速さ
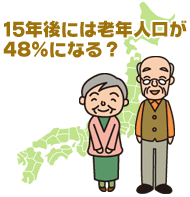 日本は今、人口が減少していると共に、高齢の方がどんどん増えています。 日本は今、人口が減少していると共に、高齢の方がどんどん増えています。
今のペースで行くと、毎年、0.5%づつ減少し、15年後には48%の老年人口を抱えるようになってしまいます。
日本の高齢化のスピードは、世界でも稀に見る速さなのです。
1970年には7%だった、65歳以上の人口の割合が、1994年には14%に増えています。
わずか24年で倍増しています。
「住宅基本法」の登場
この状況に対応し、国の住宅政策も変わってきています。
40年に渡って行われてきた「住宅建設5ヵ年計画」は、2005年に終了し、
(「住宅建設5ヵ年計画」については第三回目のコラムをご覧ください)
新たに「住宅基本法」が登場しました。
「住宅基本法」の目的は2つ、「住宅の長寿命化」と「中古住宅の活性化」です。
全国への計画として、2006年から2016年まで10年間、住宅に関する様々な政策が行われますが、
基本は、この「住宅基本法」に基づいて行われています。
日本は「計画経済」の上に成り立っています。(いろいろな意見はありますが)
量が減ったら、質の向上を目指すのは、何の業種形態でも同じです。
国としても、量の減少→質の減少とならないように、指針を作成して、質の向上を目指しているのです。
今まで、民間の業者へ委ねていた「スクラップ&ビルド(作っては壊して)」の政策は、既に転換してしまっている訳です。
人口が減っているのに、家を作っては壊している場合では無いですからね。
今後、人口・世帯数は減少して行きますが、その一方で住宅のストックと老人は増えていく、
その流れに対応するために作られたのが「住宅基本法」なのです。
次回は、この「住宅基本法」について、もっと詳しくお話したいと思います。
【続く】
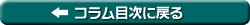 |