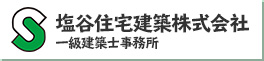家を購入する際、多くの人が利用するであろう「住宅ローン」。この住宅ローンも元々はアメリカから来たものなのですが、日本とアメリカでは仕組みが随分と違います。
今回は、この「住宅ローン」についてお話したいと思います。
建築に関する法律の「建築基準法」「建築士法」日本も戦後の復興を成し遂げ、1960年代には先進国の仲間入りを果たしました。
住宅においても、さまざまな法律の変遷を経て現在があります。
しかしながら、現在でも変わらないものがあります。それは「住宅ローン」です。
 多くの人々が住宅を購入したり、建築する際に利用する住宅ローンの基礎は「住宅金融公庫」が作りました。 多くの人々が住宅を購入したり、建築する際に利用する住宅ローンの基礎は「住宅金融公庫」が作りました。
いまでこそ、さまざまな金融商品がありますが、基本は住宅金融公庫の創り上げた仕組みが今でも生きています。
住宅ローンは、住宅や土地を担保に金融機関からお金を融通してもらうシステムと思われている方が多いと思います。
それならば、なぜ住宅ローンを支払えずに自殺したり破たんし一家離散するような悲劇が起きるのでしょう。
もろもろの仕組みを作った本家のアメリカでは、「ノンリコースローン」という住宅ローンの仕組みが基本です。
ノンリコースローンは、住宅や土地の価値に対して融資を行い、その他の財産への債務履行請求は無いので、借りた人々は家のローンが支払えなくなれば「FOR SALE」の看板を前にたて出ていけばそれで終わりです。なんのしがらみもありません。
ところが日本はどうでしょう。
お金を借りるのは大変です。連帯保証人に個人保証を行い、生命保険を掛けさせられ、おまけに抵当権をつけられ、火災保険には質権まで設定されます。
担保が足りなければ、連帯保証人の数を増やし、親子で返済を行い
逃げることなどできません。
日本はこのような「リコースローン」(保証人や他の返済財源からの返済を追求できる融資形態)が当たり前で、返済が滞ればその債権は回収されるために競売され、不足分は一生かかっても支払います。
個人保証ですので本人が自己破産しても連帯保証人は返済の義務があるのです。
なぜ、日本では本家本元のアメリカのノンリコースローンが根付かなかったのでしょうか?
建築三法をも整備させたのであれば、借金の方法も同様にすれば良かったはずです。
これは、まじめな日本人の気質にもよります。借りたものは返すのが当たり前という基本的なことが、契約社会の欧米人のリスクは五分五分で持つのが当たり前という考え方とは相いれなかったのかもしれません。
そんな観念的な事よりも、貸す側の金融機関にしてみれば、不動産などわからないのです。ましてや、建築や住宅の基本的なことなどどうでもよいことです。
それを、きちんと鑑定してくれる機関ももなければ、建築基準法のようなザル法では、リスクを吸収することすらできません。
ですから、日本では土地や住宅に貸すのではなく、「人」に貸すのです。
その人が、まじめなのか、どんなところに勤め、頭金をきちんと貯められる人なのかが重要なのです。
その代わりに債務者は、安い金利でお金を借りられます。
奇しくも、アメリカではサブプライム層に貸し出したローンにより窮地に立ってしまいました。
しかし、再生のチャンスがあるという事だけ見るならば素晴らしいと思います。
日本では、昨年は80万戸の住宅が供給され6〜7万件のローン破たんがあったそうです。
今後は、住宅価格の下落により悲惨な事例も多くあるかもしれません。
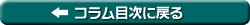 |