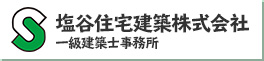
塩谷敏雄の家づくりコラム:第5回

| 第5回:住宅基本法によって日本の家の「寿命」も変わります (2010.8.22 更新) |
|---|
|
日本の住宅政策は、人口の増減と共に歩んでいます。 戦後、人口がどんどん増えてくと共に、入れ物である住宅もどんどん造り続けていました。 それも、質より量で、造って、古くなれば壊してまた建てれば良い、というのが前までの国の方針でした。 日本の家の寿命が短い(とされている)のも、そこに原因がありました。 >>詳しくはこのコラムの「第三回」を合わせてご覧ください。 しかし、近年では高齢化が進み、人口も減少してゆく見通しです。>>詳しくはこちら それに合わせ、住宅政策も大きく変わりました。 住宅基本法と長期優良住宅法 2006年に制定された住宅基本法。この法律の目的は、 ●今まで造り続け、ストック化された住宅を流通させる ●今後、ストックに成るべく建てられた住宅を出来るだけ長く使ってもらう ということです。 最近話題の、「長期優良住宅法」も、住宅基本法の一環です。 長期優良住宅法は、 「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住 宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストック を将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。」 ことを目的としており、定められた条件を満たした住宅には国から補助を受けることができます。  住宅を見てみると本当に今までの日本人の暮らしてきた生活が見えてきます。 住宅を見てみると本当に今までの日本人の暮らしてきた生活が見えてきます。まだまだ日本が青年だったころは、夢もあり庭つきの一戸建てを建てて家族を喜ばすぞと胸をふくらましていました。 しかし、家も建てて、息子が建て替えた家も世代が変わり、息子も高齢化になり多くの貯金を持ってリタイヤしているような現在の時代です。 いいものを長く使って大事に暮らしていこうということになります。 そこで、今までのストックになった家を大事に直して(リフォーム)、もし、お孫さんの世代が、また建てたいと言うなら、100年もつような家(長期優良住宅)を建てなさいというのが、現在の国の住宅方針です。 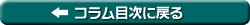 |